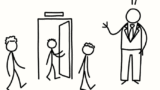プロローグ:オフィスを襲うサイコホラー?あのキラキラの輝きは、なぜ泡と消えたのか?
人事部から電話がかかってきたのは、春も半ばのことでした。「〇〇さんの退職が決まりました。一身上の都合で…」──またか。そう、彼、入社してたった3ヶ月の新戦力、〇〇君のことでした。
3ヶ月前、彼は面接室で誰よりも輝いていました。
まっすぐな眼差しで、未来への情熱を熱弁し、「御社に骨を埋めます!」とまで言い放ったあの姿は、面接官全員のハートを鷲掴みにしたものです。
「彼ならやってくれる!」疑いようのない期待感、いや、確信に似たものが私たちを支配していました。同期の中で彼の存在感は圧倒的で、「今年は当たりだ!」と誰もが信じて疑いませんでした。
しかし、オフィスで彼を見るたび、少しずつ違和感が募っていったのです。
挨拶の声はなぜかトーンが落ち、会議中はぼんやりと遠い目をしている。「入社前はもっと積極的だったのに…」そう口にするたび、私自身が過去の記憶を美化しているだけではないかとさえ感じられました。
そして3ヶ月後、彼は会社を去りました。まるで、彼の肉体に憑依していた何かが、魂を吸い尽くして消え去ったかのように。
なぜ、あの輝かしい面接時の彼と現実の彼との間には、これほどの乖離が生じるのでしょうか?
これは、私たち人間が採用活動という場で繰り広げている、人間的で滑稽な「心理戦」の結果なのではないでしょうか?
本記事では、この奇妙な現象を「就職面接憑依現象」と勝手に名付け、心理学と社会学の視点からその正体を徹底的に暴きます。
そして、その罠に嵌ってしまう企業と、自らを騙す求職者、双方の間に繰り広げられる喜劇、そして少しの悲劇の全貌を明らかにしていきます。
第1章:面接室という「閉鎖空間」で何が起きているのか?〜「面接用ペルソナ」の覚醒と進化〜
面接室とは、一見すると何の変哲もない四角い空間です。
しかし、そこは「採用」と「就職」という、人生における重要な決断が交差する、言わば「儀式の場」です。
この閉鎖空間でこそ、私たちは日頃見せない、ある「特殊な人格」を覚醒させてしまうのです。それが「面接用ペルソナ」であり、その最たる形が「憑依」です。
「ハロー効果」の爆発:面接官を狂わせる「キラキラ濾過装置」
あなたは、ある一面が優れていると、他の面も優れているように錯覚してしまう経験はありませんか?
これが心理学で言う「ハロー効果」です。そして面接室こそ、このハロー効果が最大限に爆発する空間なのです。
求職者は、人生の全てをかけた「採用されたい」という強烈な動機に駆られます。彼らは面接直前、インターネットや書籍、さらには「内定をもらった友人の振る舞い」といったあらゆる情報をかき集め、「最も採用されやすい自分」という理想の人物像を形成します。
声のトーン、話し方、眼差し、相槌のタイミング、姿勢、全てが「採用されろ!」という目標のために最適化されます。
彼らは、面接官が発したどんな質問に対しても、まるで予め入力されていたかのように流暢で、ポジティブで、建設的な回答を繰り出します。
その目からは希望が溢れ、その言葉からは情熱が滴り落ちます。これらを面接官は、脳内にある「キラキラ濾過装置」を通して見ているため、「彼こそが理想の人材だ!」という盲信に陥ってしまうのです。
「超本気」の定義:脳内ドーパミン全開状態のカン違い
では、あの面接での「超本気」とは何だったのでしょうか?
本記事では、それを「採用という報酬を得るために、一時的に脳内ドーパミンが全開となり、自己能力を最大限に(しかし、しばしば過大に)信じ込んでいる状態」と定義します。
この時、求職者の脳は「理想化モード」に突入しています。
例えば、本来は単調なデータ入力業務であっても、「御社でこのデータを入力することは、お客様の笑顔に直結する重要な業務だと認識しております!」と、宇宙の真理を見出したかのような言葉が出てきます。
徹夜続きの業務に関しても、「はい、乗り越えます!むしろやりがいを感じます!」と、異様な熱意を見せます。
このドーパミンによって強化された「超本気」は、面接官の目には確かに魅力的に映ります。
しかし、この燃料はあくまで「短期集中型」で、永続性は保証されません。残念ながら、これは一種のカン違いだったのです。
憑依の始まり:身体に乗っかる「最適化された合格者人格」
そして、極めつけが「憑依」です。
面接室という特別な舞台において、彼らの肉体は、自らが「採用されるため」に理想化された「誰か」の操り人形と化します。それはまるで、スポーツの試合中にゾーンに入って身体能力以上のパフォーマンスを発揮するのにも似ています。
その場にいるのは、紛れもなく応募者本人。
しかし、その話し方、表情、身振り手振りは、まるで彼の中に「最適化された合格者人格」が宿ったかのように、普段の彼からは想像できないほど滑らかで完璧です。
その人格は、どんな困難も乗り越えるスーパーヒーローであり、どんな理不尽も笑顔で受け止める聖人のようです。
彼自身、この憑依状態に入ると、自らの言葉と行動が真実であるかのように錯覚します。この強力な自己暗示こそが、「就職面接憑依現象」の恐ろしさなのです。
第2章:憑依現象が作り出す「幻想の相互作用」〜なぜ、採用側も騙されるのか?〜
面接で放たれる「超本気」のエネルギーは、決して一方通行ではありません。求職者が憑依する裏側で、採用側もまた、彼らの願望と希望が作り出す幻想に巻き込まれていきます。
採用側の「理想の人材飢餓」:求人票の闇と渇望
採用担当者も人間です。
「人手不足を解消したい」「とにかく良い人材が欲しい」「この大変な業務をテキパキこなしてくれる人材よ、来い!」──そういった切実な願望を抱えています。
連日の残業、山積する退職者の後始末、求人票作成業務…まさに心が荒野と化した彼らの前に現れた「超本気」の応募者は、まさにオアシスのよう。
「あぁ、この人なら…この困難な状況を救ってくれるに違いない…!」という、藁にもすがる思いが、彼らの目を曇らせ始めます。
飢えた人には、何でも美味しく見えるのです。
「確証バイアス」の悲劇:脳が見せる「いいとこどり」のマジック
ハロー効果によって「いい人だ」という第一印象を抱いた採用側は、その後、無意識のうちに「確証バイアス」の罠にはまります。
これは、「自分が信じたい情報ばかりを集め、それと矛盾する情報を無視したり軽視したりする」という脳の悪癖です。
応募者が少しでもポジティブな発言をすれば「ほら、やっぱりいい人だ!」。
些細なミスを口にしても「自分の弱みを正直に言えるなんて、なんて誠実なんだ!」と、都合よく解釈していきます。
質問の意図を正確に理解していなくても、「その意欲があれば大丈夫だろう!」と勝手に結論付けてしまう。
まさに面接官の脳内で繰り広げられる、都合の良いスクリーニング機能なのです。
プラシーボ採用:希望的観測が生み出す「未来の活躍」という妄想
面接時の「超本気」な姿を見て、採用担当者は無意識のうちに「きっと彼(彼女)は、うちの会社で大活躍してくれるだろう」という「プラシーボ採用」にかかります。
これは、あたかも偽薬を飲んだら症状が改善したかのように、応募者の表面的な魅力によって「将来の活躍」を信じ込んでしまう状態です。
しかし、ここで問題なのは、これは採用側の希望的観測であり、応募者の内面的な能力や特性とは直結しない点です。
お互いの脳内で勝手に作り上げた「最高の妄想」が相互に作用し合い、結果的に面接は最高の盛り上がりを見せるのです。
企業側は「素晴らしい人材に会えた!」と満足し、求職者側は「受かった!最高の会社だ!」と歓喜する。まさしくwin-winの、幻想に満ちた楽園です。
第3章:なぜ3ヶ月なのか?〜憑依解除と「冷徹な現実」の襲来〜
かくして採用され、希望に満ちた新生活が始まります。
しかし、「憑依」には恐ろしい有効期限が存在するのです。多くのケースで、その期限は3ヶ月という残酷な壁でした。
憑依の有効期限:非日常から日常への転落事故
面接という非日常的な儀式が終わり、入社して日常的な業務が始まると、面接官が信じたあの「超本気」の燃料は急速に枯渇し始めます。
毎日同じルーティン、予測できたような上司の説教、膨大な量のルーティンワーク。非日常の高揚感から解放されたことで、憑依されていた「最適化された合格者人格」は、自身の肉体からフッと離れていってしまいます。
するとどうでしょう、そこに現れるのは、元々の等身大の彼、いや、それ以下に感じる素の自分です。朝はなかなか起きられず、上司の指示に心の中で毒づき、スマホゲームに逃避する。
面接時の輝きはどこへやら、もはやオフィスをさまよう生気の失われた幽霊のように見えてきます。これは、期待と現実の乖離から来る、避けられない反動現象なのです。
認知的不協和の暴走:理想と現実のズレが「ここじゃない感」を加速
入社後に彼を襲うのは、面接で語られた「素晴らしい会社像」と、「目の前の厳しい現実」との間の、容赦ないズレです。
例えば、面接で語られた「チームワークが魅力!」が、蓋を開けてみれば「お互い無関心、指示は他人任せ」という現状だったり。「やりがい!」と力説された業務が、実は単純な雑務の繰り返しだったり。
この「理想と現実のギャップ」が、人間の心に大きなストレス(認知的不協和)を生み出します。そして人間は、このストレスから逃れるために、心の声が「ここは私の居場所ではない」と叫び始めます。
「私が望んだ会社じゃない!」「面接で聞いた話と違うじゃないか!」
しかし、これは会社が悪いだけではなく、自分自身が面接時に勝手に理想を膨らませすぎたという、自己責任の部分も含まれています。
この言い訳と現実逃避の無限ループが、「ここじゃない感」を異常な速度で加速させていくのです。
「違う」と悟る早さ:そして始まる、新しい憑依先を探す旅
入社後の最初の3ヶ月は、新しい環境への適応期間です。
同時に、多くのスピード退職者にとっては、「ここは、やはり自分のいるべき場所ではなかった」と「致命的な悟り」を開く期間でもあります。その期間に、彼らは新たな環境(転職市場)での再評価を求める「生存本能」を呼び覚まします。
こうなると、最早「もったいない」というサンクコスト(既に費やした時間や努力)の概念すら吹っ切れます。「このままでいることこそが損失だ!」という自己弁護が始まり、退職届が作成され、再び彼は履歴書と職務経歴書を磨き上げます。
そして、新たな会社との面接の日。彼の顔には、あの日と同じく「超本気」の輝きが再び宿るのです。それは、次の「憑依先」を見つけた、狩猟本能に燃える、無邪気な獲物探しの顔なのでした。
終章:繰り返される「憑依現象」と人類の未来
「就職面接憑依現象」。それは、求職者の「採用されたい!」という純粋な願望と、企業の「良い人材が欲しい!」という切実な願いが、奇跡的な相互作用によって生み出す、極めて人間的なドラマです。そこに悪意はありません。
しかし、無知と願望と認知バイアスが重なることですれ違い、そして哀しい結末を迎えるのです。
この現象は、もはや私たち人間が採用活動を行う以上、どこかで繰り返される、避けられないものなのかもしれません。
私たちにできるのは、この「憑依」の存在を認識すること、そして自分自身が「超本気」を演じていないか、採用担当者として「過剰な輝き」に騙されていないか、冷静に見極める眼を養うことです。
そして今日もまた、どこかの面接室で、「はじめまして!〇〇です!私が御社を志望したのは~」と、目を輝かせた一人の求職者が、新たな「就職面接憑依現象」の幕を開けようとしています。
彼の未来はどこへ向かうのでしょうか。私たちはただ、その行く末を静かに見守ることしかできないのです。